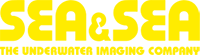AMBASSADORS
SEA&SEAアンバサダー

| 新聞社の写真記者を経て、フリーの水中写真家へ。イルカ、クジラ、サメ、アシカ、マナティ、カジキなど、大物海洋生物の撮影をテーマに世界中の海で撮影を行っている。必然的に素潜りでの撮影が多く、器材は極力小型で海水の抵抗の少ないものを好んで使用している。 |
| ●フィルムカメラ時代から愛用 |
|---|
|
「SEA&SEA社製品を使い始めたのは1990年代。フォルムの時代からです。取材の時にカメラの出し入れがしやすかった点が気に入りました。フィルムカメラ時代はNIikon F100。デジタルになってからは、CanonのEOS系で、D70、MDX 5D、MDX 7D。
SEA&SEAハウジングは 1. カメラの脱着がしやすい。 2. 軽量でかつ頑丈 の2点が気に入って、長く使い続けています。 ストロボもSEA&SEA製を愛用しています。現在、最も出番の多いのはMDX-7D Mark II + YS-D3のセットです。 SEA&SEAのストロボは、表示が完結でわかりやすいのがいいですね。YS-D3 MK IIより、YS-D3の方が個人的には、わかりやすくて好きで使っています。 |
| ●クジラ撮影にはFIsheye zoom |
|---|
|
クジラなどの大型海洋生物の撮影ではMDX-7D Mark II とFisheye zoomレンズの組み合わせがメイン機材です。
1台のカメラで、大物海洋生物を撮影するときに、8-15mmのFisheye zoomだと、生物が嫌がる距離まで近寄らなくてすみます。 フィッシュアイレンズで、クジラの親子を正面から撮影すると、子供がデフォルメされて大きくなりすぎて、親子の雰囲気が出ないのですが、このセットの場合、テレ端(24mm)で距離を保って撮影すると、仲のいい親子の雰囲気を出すことができます。 以前は、フィッシュアイレンズと、ショートズームの2台持ちでしたが、このセットを使用するようになってからは、1台ですむようになりました。荷物の重量制限が厳しい海外ロケでも、マクロレンズやストロボなど他の機材を持って行けます。 |
| ●水中撮影器材に求めるのは機動性 |
|---|
|
素潜りで撮影するときの扱いやすさを重視しています。潜りやすい重さ、浮力、コンパクトさ、操作性、カメラの取り外しやすさなど、ですね。重量級路線のハウジングもありますが、SEA&SEAには、素潜りでも操作しやすい方向性をさらに模索してもらいたいと個人的には思っています。
日本でも、イルカに続き、クジラと泳ぐのがブームになって来ていますし、素潜りで水中撮影する人も年々増えてきています。スクーバダイビングとは違ったSEA&SEAブランドの方向性を期待しています。 ミラーレス一眼も気にはなっていますが、大物海洋生物の撮影では、長いと3時間も4時間も海で撮影していることがあるので、バッテリーの持ちは重要な要素の一つです。バッテリーの持ちがもう少し改善されないと、ミラーレス一眼にはなかなか踏み出せないでいます。 |